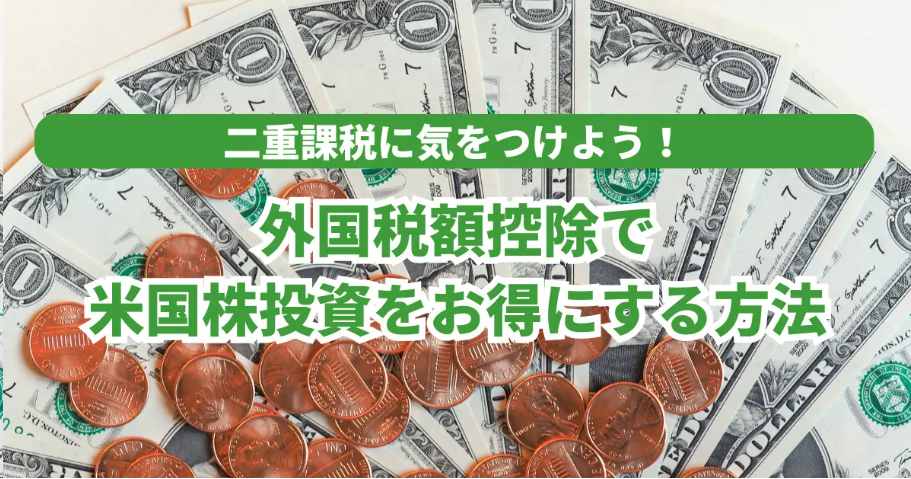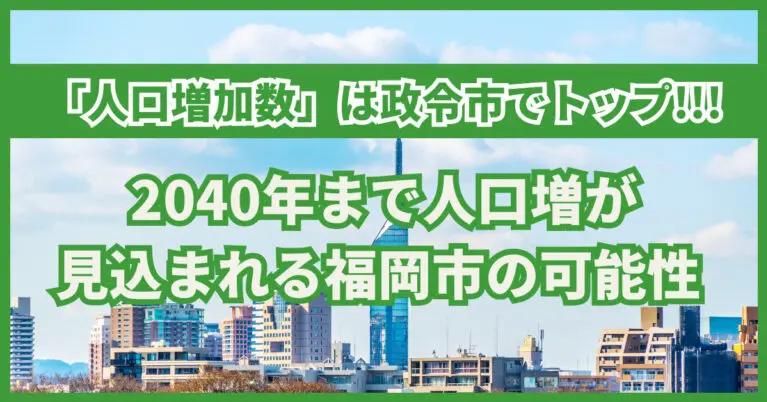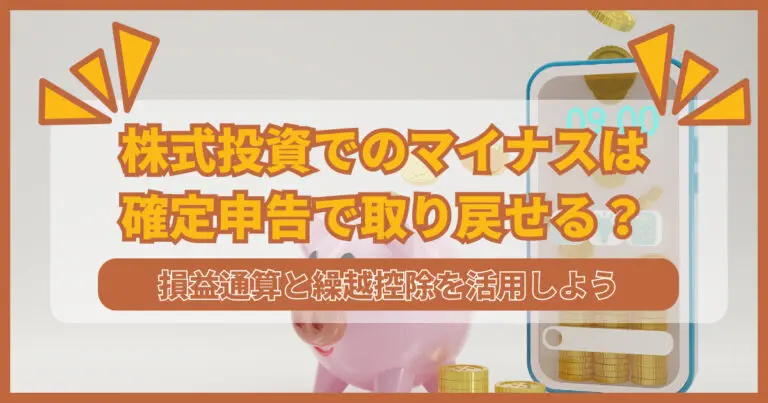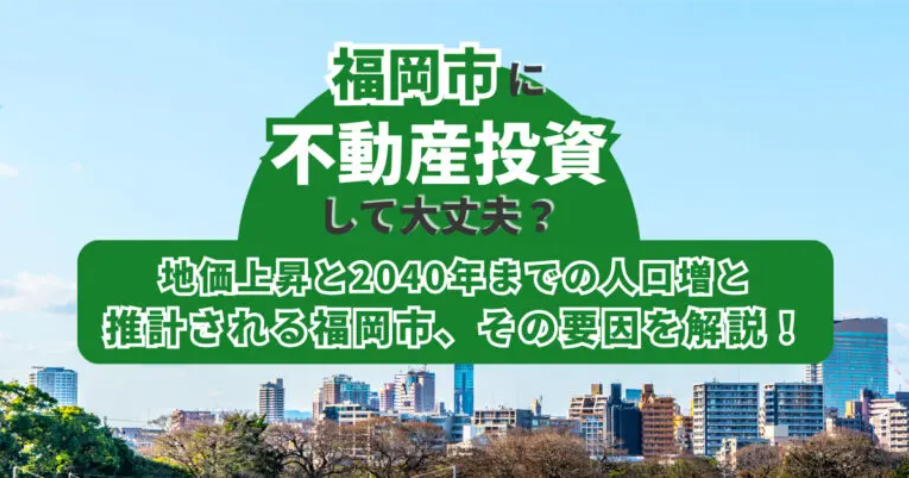不動産クラウドファンディングで失敗する4つの要因
不動産クラウドファンディングが失敗し、利益を得られなくなってしまう要因を知っておくことは大切です。
失敗する要因は以下の4つです。
(1)運営会社に不測の事態
(2)不動産業界の影響
(3)案件不動産の空室率の増加や営業問題
(4)商品が人気で出資できないそれぞれを説明します。
(1)運営会社に不測の事態
不動産クラウドファンディングの運営事業者に、何らかの不測の事態が生じて失敗する場合があります。
例えば、会社の不祥事や倒産などです。
過去には、大手不動産会社の不動産事業における問題で、業務停止命令を受けた為に、問題がなかった不動産クラウドファンディング事業まで停止せざるを得なかった事例がありました。
不測の事態によって事業撤退になれば、元本割れや出資金が戻らないといった事態になってしまいます。
(2)不動産業界の影響
投資対象が不動産である以上、不動産業界悪化の影響を受けてしまうのも失敗する要因です。
不動産業界の状況が悪化すれば、不動産価値の低下による元本割れで損失が出てしまったり、なかなか売却できず出資金の返済に遅れが生じてしまいます。
売却がスムーズに進まない場合は、運用期間を延長し、延長分も分配金を得られるような契約内容もあります。
しかし、売却が上手く進んでいないので、予定の金額よりも売却金額が低くなる可能性はあるでしょう。
(3)案件不動産の空室率の増加や営業問題
案件不動産の空室率が増加したり、ホテルやレジャー施設の営業状況が悪化すると、想定利回りが大幅に下落し、利益が出ない場合があります。
不動産クラウドファンディングの分配金は家賃収入や事業収入です。
投資した不動産の空室率や経営状況は大きく影響し、想定した分配金を受け取れない結果となります。
(4)商品が人気で出資できない
不動産クラウドファンディングが人気の投資手法であるために、投資できない場合があります。
不動産クラウドファンディングは募集金額や口数が決まっており、募集後すぐに完売してしまったり、応募者多数により抽選になるため、抽選ではずれてしまい、希望の不動産に投資できないことがあります。
せっかく不動産クラウドファンディングサービスに登録しても、投資ができなければ資金運用もできず、利益も得られません。
不動産クラウドファンディングで起こりうる5つの失敗例
不動産クラウドファンディングで起こりうる失敗例を解説します。主には以下の5つです。
(1)元本割れする
(2)入金が遅れる
(3)途中解約ができない
(4)事業者が倒産する
(5)確定申告を忘れる
それぞれを見ていきましょう。
(1)元本割れする
不動産クラウドファンディングは投資であるため、元本が保証されていません。
ファンド運用後に売却し、売却価格が出資金総額よりも低いと、元本は全額戻ってこない可能性があります。
売却が想定金額よりも低くなってしまった場合のリスクを避けるために、運営事業者は「優先劣後方式」を取り入れています。
優先劣後方式とは、投資家を優先出資者、運営事業者を劣後出資者とし、元本割れが起こっても、劣後出資者の出資金から先に損失を計上する仕組みです。
(2)入金が遅れる
失敗例の1つとして、入金が遅れるケースです。入金が遅れることで、予定していた支払いができない可能性が高まります。
さらに、不動産の売却に時間がかかることで、資金調達が予定通りにいかず、次の行動に移せなくなってしまう可能性も出てしまいます。
不動産クラウドファンディングで失敗しないためにも、ある程度の余裕資金を集めて行うのがおすすめです。
(3)途中解約ができない
不動産クラウドファンディングは、原則途中解約ができません。運用中に資金が必要となっても、現金化はできないため、失敗したと感じる方もいます。
運用期間は短いものでは3ヶ月、長いものでは1年以上に及ぶものもあります。
途中解約ができないことを前提として資金繰りを考えましょう。
(4)事業者が倒産する
事業者が倒産すると不動産クラウドファンディングが失敗するケースがあります。
基本的に不動産クラウドファンディングの事業者は、厳しい国の審査を通過しているため、倒産する確率は低いです。しかし、倒産する可能性はゼロではありません。
事業者が倒産してしまうと、不動産クラウドファンディングに費やした費用が無駄になってしまいます。
不動産クラウドファンディングを失敗させないためにも、事業者は吟味しましょう。
(5)確定申告を忘れる
不動産クラウドファンディングで収入を得ると確定申告が必要な場合があります。以下の項目に一つでも当てはまると確定申告が必要です。
●雑所得が合計で20万円以上の人
●2か所以上の就業先から一定の収入を得ている人
●年収2,000万円以上の会社員
●青色申告を利用している人
●ふるさと納税でワンストップ納税を適用しない人
●医療費控除を受ける人
●不動産所得などその他の所得があった人
確定申告を行うべき人がしない場合は、追徴課税が発生する可能性があります。
無駄なお金を発生させないためにも、必ず自分が確定申告が必要な人か確認するようにしましょう。
なお、不動産クラウドファンディングの分配金は、匿名組合型が雑所得、任意組合型が不動産所得です。
これらの詳しい違いは以下の記事で解説しています。気になる方は最後までご覧ください。
不動産クラウドファンディングの匿名組合型と任意組合型とは?違いやおすすめを解説

失敗しない不動産クラウドファンディングの7つのコツ
不動産クラウドファンディングが失敗しないコツを7つ紹介します。
(1)運営事業者をしっかり調べる
(2)投資する不動産の情報は十分か
(3)案件数が多い
(4)分散投資する
(5)利回りを求めすぎない
(6)自分にあった運用期間を選ぶ
(7)優先劣後方式を取り入れている
失敗しないことは不動産クラウドファンディングを始めるうえで重要です。しっかりと理解して、成功させましょう。
(1)運営事業者をしっかり調べる
不動産クラウドファンディングを運営する会社について、公開されている情報をしっかり確認しましょう。
大手企業だから必ずしも安心ということではありません。
具体的には、今までの不動産運用の実績や、経営状況、創立日、過去の不祥事などをチェックするのがオススメです。
不動産業界で長年の経験がある会社は、知識やノウハウを持っていると判断できます。
なお、不動産クラウドファンディングは福岡がアツイと言われています。以下の記事では、福岡市での不動産業者の選び方を詳しく解説しています。事業者選びの参考になりますので、ぜひお読みください。

(2)投資する不動産の情報は十分か
案件不動産の情報は投資するかどうかの重要な判断基準となるため、十分な情報量を公開している案件がおすすめです。
住所や面積、築年数や使用目的など情報量が多いほど、案件不動産が収益を求められる不動産かどうか、判断しやすくなります。
公開されている情報が正しい情報か慎重な判断も必要になります。
(3)案件数が多い
運営会社は、案件数や物件の種類、募集頻度が多い会社を選びましょう。
不動産クラウドファンディングは人気がある投資手法なので、案件数が少ないといい条件での投資が難しく、妥協せざるを得ません。
案件数が多ければ、自分の条件にあった案件を見つけられ、投資する機会が増えます。
案件の規模にも注目しましょう。数億円規模の案件であれば、すぐに募集締切になるようなことはありません。投資のチャンスも広がり、資金をしっかり運用できます。
(4)分散投資する
不動産クラウドファンディングは分散投資をして、リスクも分散しましょう。
1つの運営会社のみで投資をしていると、運営会社に不測の事態が起こった際に、大きな損失を受けてしまいます。
複数のクラウドファンディングサービスに登録して投資すれば、損失を避けられます。
運営会社のみならず、運用期間や案件の種類でも分散投資するのがおすすめです。
利回りの高いホテルだけに投資するのではなく、マンションにも投資すれば、安定した分配金が得られます。
さらに、分散投資は、不動産クラウドファンディングのさまざまなリスクを軽減できます。
流動性の悪さをカバーするためには、長期ばかりではなく短期にも投資することが大切です。
(5)利回りを求めすぎない
利回りが高い案件ばかりを求めすぎないのもポイントの一つです。
不動産クラウドファンディングの利回り(分配率)は、平均で4〜5%程度です。
入居率が低くなったり、市況に影響され売却益が大幅に下がったりと、想定していた利回りではなくなってしまう場合があります。
利回りが高ければ、リスクも高くなり、受ける損失も大きくなります。
利回りが高い案件は魅力的ですが、安全性も考え、自分が許容できる範囲のリスクでなければいけません。
また、利回りとしてよく使われている「予定分配率」とは、投資額に対する収益の見込み(年利)で、実際に収益を保証するものではありません。
予定利回りや分配率は、あくまでも目安ということを理解しておきましょう。
利回りについての詳しい説明は以下のコラムをお読みください。
不動産クラウドファンディングの利回りってどれくらい?
(6)自分にあった運用期間を選ぶ
不動産クラウドファンディングにおける運用期間とは、投資家から集めた資金で、不動産クラウドファンディング事業者が案件不動産を運用する期間のことです。
ほとんどの不動産クラウドファンディングで運用期間は定められています。
不動産クラウドファンディングの運用期間は短期と長期があるので、自分に合った運用期間を選びましょう。
一般的に、短期のものは3か月〜1年、長期のもので2年〜3年が運用期間の目安です。
短期の案件は分配金を早く回収できるため、新しい投資ができたり、先の見えない業界の影響を受けにくいといったメリットがありますが、すぐに次の良い案件が見つかるとは限りません。
長期の案件は、資金を長く運用でき、運用中はずっと配当金を受け取れます。しかし、中途解約ができない場合や手間がかかる場合があるため、急にお金が必要になった時に困ってしまうことがあります。
不動産クラウドファンディングは余剰資金で投資をし、短期と長期それぞれのメリット・デメリットを参考に、自分に合った運用期間を選ぶことが大切です。
運用期間についての詳しい説明は以下のコラムをお読みください。
不動産クラウドファンディングの最適な運用期間は?短期・長期の特徴を知って投資してみよう!
(7)優先劣後方式を取り入れている
不動産クラウドファンディングにおける優先劣後方式とは、投資家の損失リスクを抑えるための仕組みです。
優先劣後方式では、優先出資者である「投資家」と劣後出資者である「事業者」の出資金を分けて扱います。
運用において利益が発生すれば、「投資家」「事業者」ともに利益配分を受け取れますが運用において損失が発生した場合には、投資家への償還が優先され、投資家は元本割れするリスクが低く、損失を被りにくいといえます。
優先劣後方式についての詳しい説明は以下のコラムをお読みください。
不動産クラウドファンディングにおける優先劣後方式とは?
不動産クラウドファンディングなら「えんfunding」
えんfundingは、株式会社えんホールディングスが運営する不動産クラウドファンディングです。
えんfundingの不動産クラウドファンディングの利回りは平均4〜9%前後と非常に高く、「優先劣後方式」を採用することで、投資家へのリスクを最大限に抑えています。
また、不動産事業者として創業以来、30年にわたって物件選定・運用を行ってきた経験があります。
価値が下がりにくく、人気の高いデザイナーズマンションを厳選して運用するため、専門知識がなくても安心して始められます。
1口1万円からの少額出資が可能で、優先劣後システムももちろん導入しています。
えんfundingでは体験レポートが提供され、不動産投資の知識も身につけられます。
そして、大きな特徴は福岡市に特化した不動産クラウドファンディングであること。
福岡は地方都市の中でも人口増加の見込みがあり、地価も上昇しており、不動産投資の注目の都市でもあります。
えんfundingで不動産クラウドファンディングを始めてみてはいかがでしょうか始めてみましょう。
不動産投資が学べる漫画など特典プレゼント中
漫画だから分かりやすい。不動産投資が学べる特典を無料プレゼント。お申込みはこちらから。
特典提供元:株式会社えん


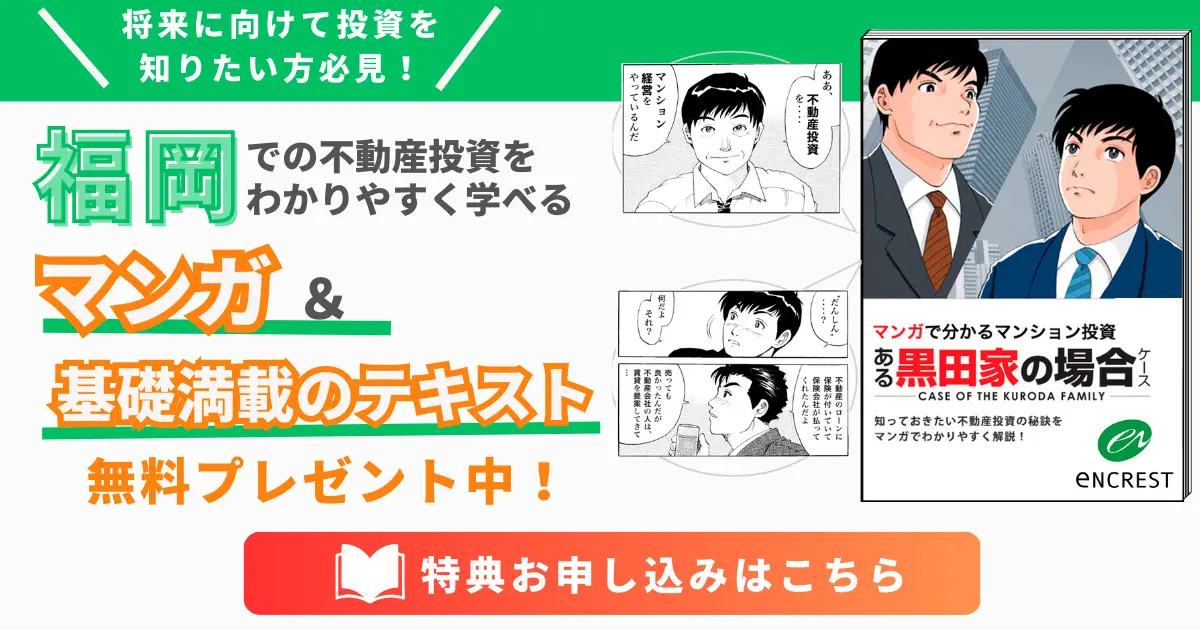

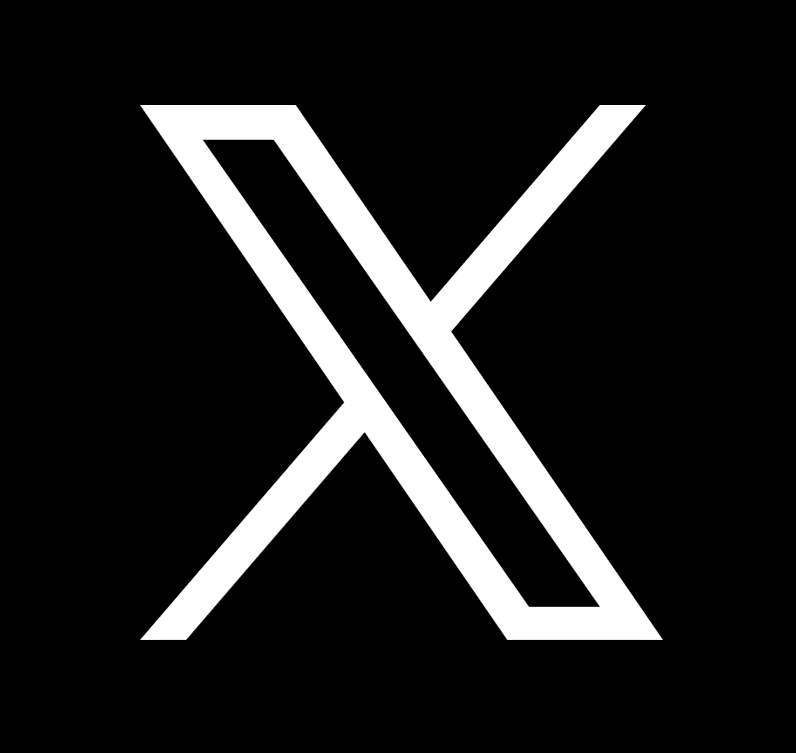
 関連コラム記事
関連コラム記事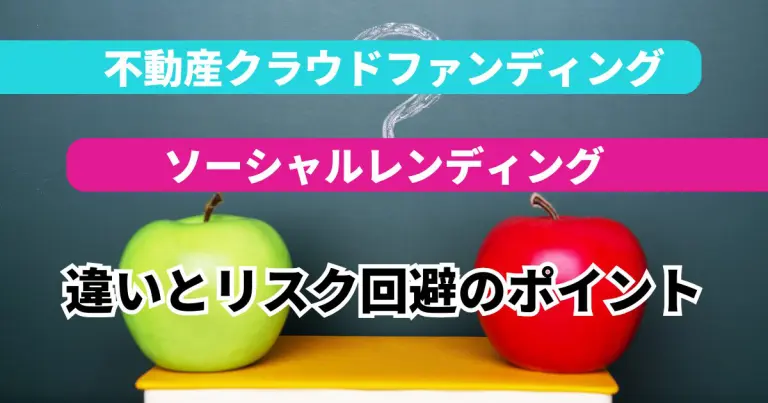
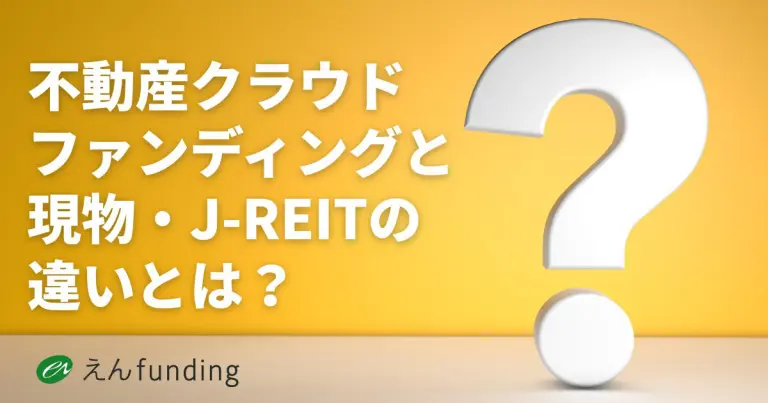
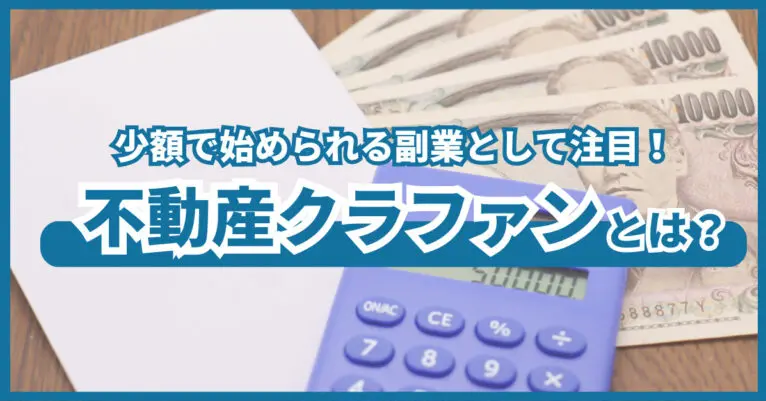
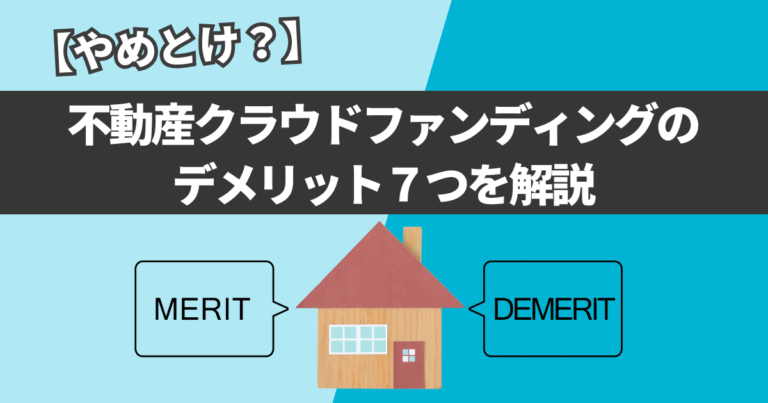

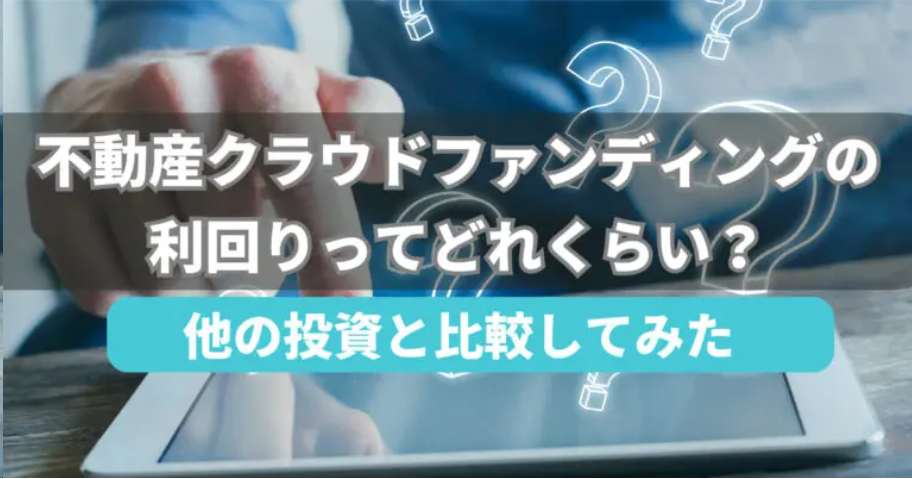

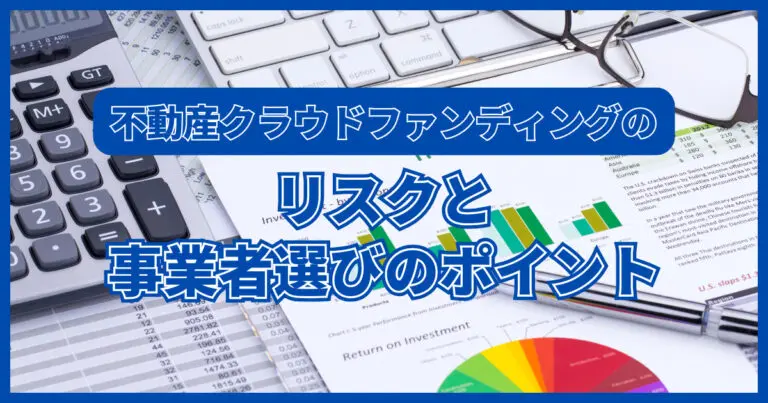

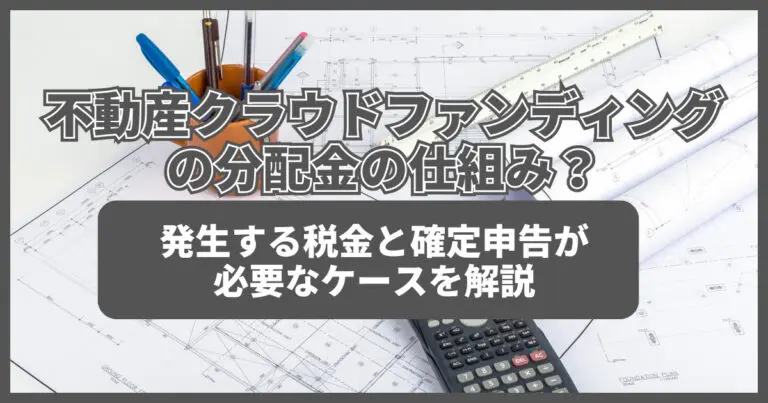
 人気コラム記事ランキング
人気コラム記事ランキング