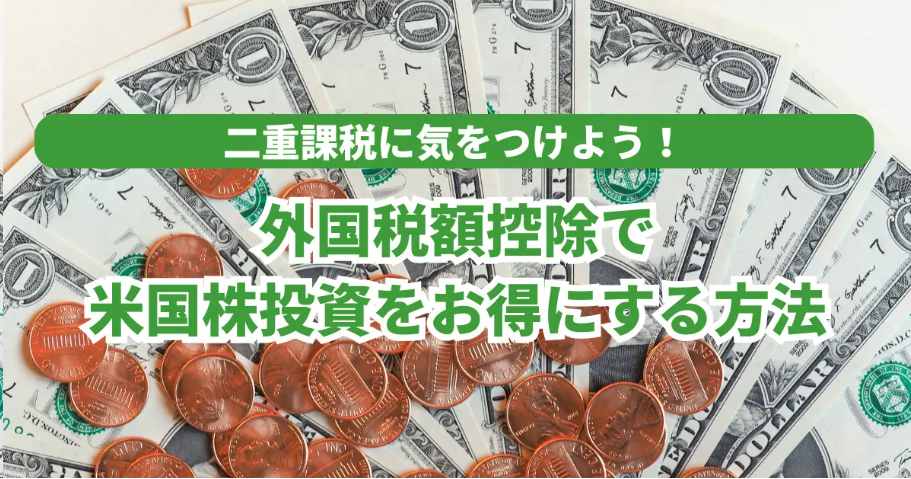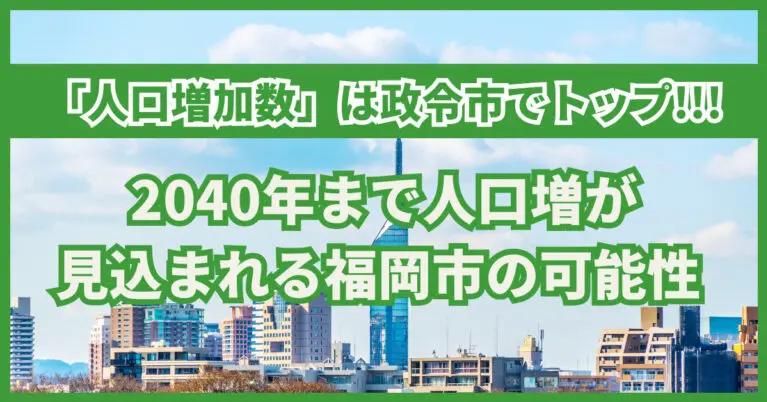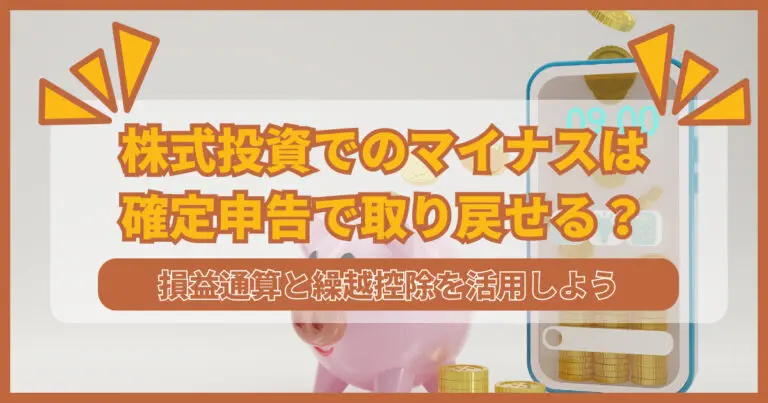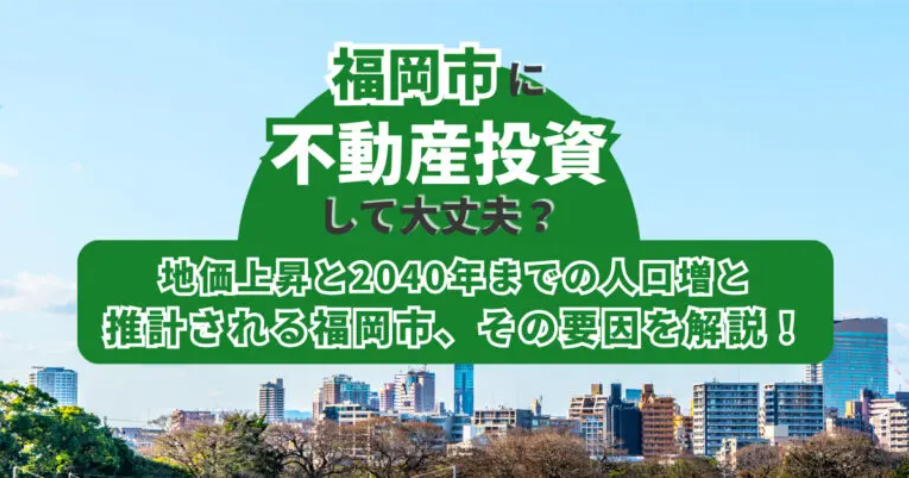不動産投資で知っておくべき10個のリスク
不動産投資を行う上で発生しうるリスクを10個に絞って解説していきます。実際に不動産投資を行ってから後悔することがないように、事前にリスクを知り対策を講じるようにしましょう。
1.空室リスク
2.家賃滞納リスク
3.家賃下落リスク
4.修繕リスク
5.火災リスク
6.地震リスク
7.老朽化リスク
8.不動産価格下落リスク
9.金利上昇リスク
10.倒産リスク
1.空室リスク
空室リスクとは、所有している物件の入居者が見つからず空室が発生し、家賃収入を得られないリスクのことです。
空室のあいだは家賃収入が得られないと同時に、不動産の維持費やローンの返済で赤字状態に陥る可能性があります。
空室が長期間続いたり、空室率が高くなったりすると、赤字状態はさらに悪化してしまいます。
不動産投資の主な利益は家賃収入であるため、最も避けたいリスクです。
空室リスクを軽減するには以下の方法が挙げられます。
・好立地の物件を選ぶ
・入居付けを得意とする賃貸管理会社を選ぶ
好立地の物件は需要が高いため、空室リスクを軽減できます。
物件の需要が長期的に期待できるかどうかという点にも注目することが大切です。
また、入居付けを得意とする賃貸管理会社を選ぶことでも、空室リスクを軽減できます。
賃貸管理会社を選ぶ際は各会社が運用する物件の入居率を確認し、少なくとも入居率が95%以上の賃貸管理会社を選びましょう。
なお、以下の記事では賃貸管理会社の選び方を詳しく解説しています。気になる方はご覧ください。
成功する不動産投資の鍵!管理会社選びのポイントと失敗しないコツ
2.家賃滞納リスク
家賃滞納リスクとは、入居者が家賃を滞納することで、家賃収入を得られないリスクのことです。
家賃の支払いが遅れれば、おのずと収入を得られるタイミングも遅れてしまいます。
最悪の場合、入居者から家賃を回収できないまま、諦めざるを得ないケースもあります。
日本賃貸住宅管理協会によると、2023年度における月末の家賃滞納率は全国で1.2%でした。
家賃の払い忘れであれば、催促することですぐに回収できますが、そうでないケースもあることを忘れてはいけません。
参照:日本賃貸住宅管理協会「賃貸住宅景況調査 2023年度」
家賃滞納リスクを軽減するには以下の方法が挙げられます。
・入居時の審査が信頼できる賃貸管理会社を選ぶ
・「家賃保証会社への加入」を入居条件にする
入居者募集を賃貸管理会社に任せている場合、入居者の審査も賃貸管理会社が行います。
そのため、入居時の審査が信頼できる会社を選びましょう。
「入居時の審査に明確な基準を設けているか」や、「家賃滞納への対応はしてくれるのか」を事前に確認しておくことが大切です。
また、家賃保証会社への加入を入居条件にするという軽減方法もあります。
入居者が家賃保証会社へ加入することで、入居者から家賃が支払われなかった場合は、家賃保証会社から家賃が支払われるという仕組みです。
家賃滞納リスクをより確実に軽減したい方におすすめです。
3.家賃下落リスク
家賃下落リスクとは、建物が経年劣化していくにつれて家賃が下落するリスクのことです。
家賃が下落すれば、もちろん得られる家賃収入も少なくなります。
一般的には、1年あたり1%前後が下落すると言われています。
新築と比較して築10年の建物は約10%、築20年の建物は約20%下落する計算となります。
ただ、築20年を超えたあたりから家賃の下落率は緩やかになるというのが、よくみられる傾向です。
参照:三井住友トラスト基礎研究所「経年劣化が住宅賃料に与える影響とその理由|レポート・コラム」
家賃下落リスクを軽減するには以下の方法が挙げられます。
(1)周辺の家賃相場を調べる
(2)一人暮らし向けの物件を選ぶ
(3)設備の充実している物件を選ぶ
それぞれを見ていきましょう。
(1)周辺の家賃相場を調べる
物件購入予定の周辺の新築時と、築年数の経った物件の家賃相場を調べることで、物件購入時から家賃が大きく下落するリスクを軽減できます。
新築時の家賃と築10年や20年の家賃を比較し、下落率を確認しましょう。
大きく下がっていないエリアであれば、家賃下落リスクは低い地域と言えます。
一方で大きく下落している場合は、家賃下落リスクが高くなるため購入は慎重になることをおすすめします。
過去のデータからではこれから先の状況をすべて把握するのは難しいですが、参考にすることで家賃下落リスクを少しでも抑えることが可能です。
また、地価が上がっている地域か確認しましょう。
地価が上がっていれば不動産の価値も上がっていきます。
通常であれば家賃が下落していきますが、不動産の価値が上がっていけば家賃下落リスクを抑えることも可能です。
不動産価格の推移について、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方はぜひお読み下さい。
高騰する不動産市場!今このタイミングで不動産投資をはじめるのはあり!?なし!?
(2)一人暮らし向けの物件を選ぶ
一人暮らし向けの物件は家賃下落リスクが低いと言われています。
三井住友トラスト基礎研究所によれば、経年劣化が賃料に与える影響は年1%程度で、築20年を超えるとほぼ横ばいになるという結果が出ています。
また、築20年以降の家賃下落率は、ファミリー向け物件より18㎡以上30㎡未満の一人暮らし向け物件の方が、下落率は低くなる傾向があるようです。
参照:三井住友トラスト基礎研究所「経年劣化が住宅賃料に与える影響とその理由|レポート・コラム」
このように一人暮らし向けの物件を選ぶことで、家賃下落リスクを抑えやすくなります。
(3)入居者が求める設備がある物件を選ぶ
入居者が求めている設備を充実させることで、空室リスクを減らせると同時に家賃下落リスクも抑えることが可能です。
追加するのは難しいですが、物件購入時に入居者が求めている設備が導入されているか確認するようにしましょう。
特に入居者は無料で使えるWiFi環境や宅配ボックスがあると家賃下落リスクを抑えやすくなります。
ここで注目したいのが、人口増加が続く、福岡市内の物件の家賃がどんどん上昇傾向にあるということ。
福岡市中央区にある物件を例に見てみると、対象物件の「エンクレスト天神FOCUS」は、福岡最大の商業エリアである「天神」と歓楽街の「中洲」に挟まれた春吉エリアマンションです。
えん賃貸管理の管理戸数は77戸となっており、その中で、空室の戸数は2戸となっていますので、入居率は97.4%です。(2025年4月18日 時点)
空室となっている部屋の前入居者の家賃額と現在の募集家賃額を比較します。
空室予定① … 家賃65,000円 → 家賃75,000円(10,000円 UP)
空室予定② … 家賃65,000円 → 家賃73,000円(8,000円 UP)
2部屋とも8,000円〜10,000円の賃料上昇となっています。
退去予告が出ている部屋の戸数は2戸となっており、その部屋の現入居者の家賃額と今後の募集家賃額を比較します。
退去予定① … 家賃58,000円 → 家賃73,000円(15,000円 UP)
退去予定② … 家賃67,000円 → 家賃75,000円(8,000円 UP)
2部屋とも8,000円〜15,000円の賃料上昇となっています。
新たに募集する4件全てで賃料上昇となっています。
このように物件の選び方次第では家賃下落リスクを避けることもできます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
今注目されている不動産投資の成功の鍵を握る「入居率」!高入居率物件の選び方
4.修繕リスク
修繕リスクとは、物件の修繕費用が発生するリスクのことです。物件の築年数にかかわらず、ある程度の時間が経てば修繕が必要になるタイミングがあります。
例としては、「配管の交換」「外壁や屋根の塗装」「エアコンや給湯器の取替」などが挙げられます。
このように、修繕の種類はさまざまで、長期的に物件を運用するのであれば、必ず直面する問題です。
修繕リスクは、建物の経年劣化とともに必ず発生するため、修繕費用をゼロにすることは困難です。
そのため、修繕リスクの軽減方法としては、運用開始時から修繕費用を積み立てておくという方法が挙げられます。
積立額の目安は、家賃収入の約3~5%といわれています。このように、修繕リスクを軽減するには計画性が大切です。
5.火災リスク
火災リスクとは、火災が起こることで建物に被害が及ぶリスクのことです。
ローン返済中に火災で建物が焼失してしまえば、家賃収入を得られないままローンの返済だけが続くことになります。
被害が建物の一部に収まったとしても、リフォームや修繕にかかるコストは莫大です。
火災リスクを軽減するには、火災に強い物件を選ぶことと、火災保険へ加入するという方法が挙げられます。
木造物件は価格が比較的安価となりますが、火災リスクの観点からはおすすめできません。
物件購入時に火災保険に加入しておくことで、火災だけでなく、台風や浸水などの自然災害が起こった際、保険金が支払われます。
そのため、家賃収入が得られなくなった場合でも、保険金で対応可能です。
ただ、契約する保険によって保険金が支払われる条件や金額が異なるため、条件や金額については事前に確認しましょう。
6.地震リスク
地震リスクとは、地震が起こることで建物に被害が及ぶリスクのことです。
火災リスク同様、地震によって建物が倒壊してしまえば、家賃収入を得られなくなります。
特に日本は地震大国であることから、地震リスクへの対策は必須です。
地震リスクを軽減するには以下の方法が挙げられます。
・耐震性の高い物件を選ぶ
・地盤の強い地域にある物件を選ぶ
・地震保険に加入する
耐震性の高さは、「新耐震基準」で作られた物件かどうかで判断します。
新耐震基準とは、建物が「震度5程度で損傷しないこと」「震度6~7で倒壊しないこと」を想定した基準のことです。
新耐震基準で作られた物件であれば地震による被害を最小限に抑えられます。
また、地盤の強い地域にある物件を選ぶことも、ひとつの軽減方法として挙げられます。
地盤の強い地域を調べる際は、防災科学技術研究所が提供している「J-SHIS 地震ハザードステーション」の活用がおすすめです。
同サイトでは、地震が起こった際の揺れやすさが地域ごとに把握できます。
上記2つの地震が起こった際の建物への被害を最小限に抑える対策にくわえて、地震保険へ加入しておくとさらに安心です。
地震によって建物に被害が出た際、保険金が支払われます。
ただ、火災保険と同様に、契約する保険によって保険金が支払われる条件や金額が異なるため、事前に確認しましょう。
参照:国土交通省「新耐震基準の概要」
7.老朽化リスク
老朽化リスクとは、建物が老朽化することによって家賃の下落や修繕費用が発生するリスクのことです。
老朽化によって「家賃下落リスク」「修繕リスク」を引き起こすとも言い換えられます。
老朽化リスクを軽減するには以下の方法が挙げられます。
・定期的なメンテナンスを行う
・修繕費用を積み立てておく
建物の老朽化は免れません。
大幅な老朽化が進めば、家賃の下落が起こったり修繕が必要になったりするため、定期的にメンテナンスを行い、老朽化が進まないような対策をしましょう。
また、修繕リスクと同様、運用開始時から修繕費用を積み立てておくことも大切です。
突然修繕が必要になった場合でも、対応できるようにしましょう。
8.不動産価格下落リスク
不動産価格下落リスクとは、不動産の価格が下落し、売却価格が購入価格を下回ってしまうリスクです。
不動産投資は、継続的に運用することで家賃収入を得る方法以外にも、購入価格より高い価格で売却し、その差額を売却益として得る方法があります。
ただ、不動産価格が下落すれば、売却価格が購入価格を下回り、利益は発生しません。
不動産価格下落リスクを軽減するには以下の方法が挙げられます。
・好立地の物件を選ぶ
・安定した人気を持つブランドマンションを選ぶ
不動産の価値が大きく低下することがないよう、好立地の物件を選びましょう。
好立地な物件は継続的に需要が見込まれるため、不動産価格が大きく下落することはありません。
ブランドマンションの魅力は建築物としてのデザイン性や品質の高さだけではありません。
新規入居者の募集など、営業活動やマーケティング力の強さ、入居者へのサポートが充実していることで信頼を蓄積できる点もその魅力であり、価値の維持、向上の取り組みを行っているため、不動産価格の下落が少ないといえます。
以下の記事では、福岡市の不動産投資でブランドマンションが人気の理由と、物件を選ぶ際のポイントを詳しく解説しています。
ぜひともお読みください。
福岡の不動産投資はブランドマンションが人気!おすすめ理由は資産価値
9.金利上昇リスク
物件の購入にローンを利用する際、金利が発生します。
金利上昇リスクは、ローンの金利が上昇し、支払い額が増加するリスクのことです。
金利が上昇すれば想定していた支払総額が増えてしまいます。
また、家賃収入からローンを返済している場合は、支払いが増えることで手元に残る利益はおのずと減ってしまいます。
金利上昇リスクを軽減するには以下の方法が挙げられます。
・固定金利を選ぶ
固定金利を選んでおけば、最初に決められた金利から変動がないため、支払い額が増加する心配がありません。
なお、以下の記事では住宅ローン金利について詳しく解説しています。
気になる方は最後までお読みください。
不動産投資ローンの金利を徹底解説!初心者向けの基礎知識と金利相場
10.倒産リスク
倒産リスクとは、物件の管理を委託している賃貸管理会社が倒産してしまうリスクのことです。
管理会社が倒産してしまうと、入居者の募集や運用をオーナー本人で行う必要が出てきます。
不動産投資は本業と掛け持ちで行う方も多く、物件の管理や運用に手間を割けないケースも考えられます。
倒産リスクを軽減するには以下の方法が挙げられます。
・経営状況が安定した管理会社を選ぶ
・代わりの管理会社を探す
倒産リスクを避けるには、そもそも倒産の可能性が少ない管理会社を選ぶことが大切です。
過去の管理実績を確認し、経営状況が安定した管理会社を選びましょう。
もし委託していた管理会社が倒産した場合でも、必ずしも自主管理が必要になるわけではありません。
代わりの管理会社を探すことで対処できます。
不動産投資はリスクが高いと言われる3つの原因
不動産投資はリスクが高いと言われる主な原因は以下の3つです。
1.扱う金額が大きい
2.損をした話題を耳にしやすい
3.不動産投資の投資経験者が少ない
それぞれを解説していきます。
1.扱う金額が大きい
不動産投資は動く金額が大きいため、リスクが高いと言われています。
特に不動産投資ではローンを組めるため、株式投資や投資信託など他の投資と比べるとまとまった金額を動かせる特徴があります。
ローンを組むことで、手元に100万円しかなくても1,000万円のローンを組んで不動産投資を行うことができます。
しかし、建物が壊れてしまったら1,000万円のローンが残ってしまうため、万が一を考えてリスクを高いと感じる人も多くいます。
2.損をした話題を耳にしやすい
失敗談や詐欺被害などの大きな損をした話題を耳にしやすいことも、不動産投資のリスクが高いと言われる原因の1つです。
不動産投資は動く金額が大きいため、損をした場合の金額も大きく、話題になりやすい傾向があります。
投資で100万円損をしたという話題よりも、1億円損をしたという方が注目されやすいですよね。
実際に1億円の損をすることは多くありませんが、金額の大きい話題は目につきやすいため、リスクが高いと言われやすい原因です。
3.不動産投資の経験者が少ない
実際に不動産投資を行っている人が少ないことが、リスクが高いと言われる原因の1つです。
令和元年9月27日に国土交通省から発表された資料によると、個人投資家のうち不動産投資を行っている人の割合は12.6%となっています。
この中には現物不動産しか対象となっていないため、不動産クラウドファンディングやJ-REITを行っている人は含まれていません。
投資を行っている人でさえ8人に1人程度の割合でしか不動産投資経験者はいないため、実態が見えずリスクとして考えてしまっていると思われます。
不動産投資を始めるメリット4選
不動産投資を始めるメリットを4つ紹介します。
リスク対策をしっかりと行い、不動産投資のメリットを知ることで、効率の良い投資を行えるようになります。
1.毎月の収入が増える
2.不労所得になる
3.生命保険のような効果を得られる
4.節税につながる
一つずつ見ていきましょう。
1.毎月の収入が増える
不動産投資において家賃収入を得られれば、毎月の収入が増えます。
本業の収入に加え「あと数万円欲しい」と考えている方に最適です。
また、賃貸契約は1~2年契約が多く、契約期間中に家賃が変動することはありません。
そのため、毎月安定した収入を得やすくなります。
2.不労所得になる
ローンの返済が完了した場合、家賃収入をローンの返済にあてる必要がないため、不労所得となります。
物件の管理を管理会社に委託しておけば、自主管理する必要もありません。
不動産投資における仕事といえば、家賃の振込を確認するのみです。
本業を退職した場合でも収入源があることは、将来への安心にもつながるでしょう。
3.生命保険のような効果を得られる
不動産投資で物件を購入する際、ローンを活用するのであれば「団体信用生命保険」への加入が必要になるケースがほとんどです。
この団体信用生命保険はローンの契約者が亡くなったり、支払いが困難な高度障害状態になったりした場合、ローンの返済が不要になるという仕組みです。
正確には、団体信用生命保険から出る保険金によってローンが全額清算されます。
オーナーが亡くなった場合でも物件の所有権は遺族へ移せるため、家賃収入を遺すことができることから、生命保険のような効果を得ることができます。
4.節税につながる
不動産を所有していれば、相続税の節税につながります。
資産を相続する際、相続する資産の金額に応じて税金が発生します。
ただ、不動産を相続する場合は不動産の評価額に対して相続税が発生するため、現金で相続するより相続税が少なくなるというのが全体の傾向です。
不動産の評価額の目安としていわれているのが、購入価格の約7割です。
そのため、金額に応じて発生する相続税額も抑えられます。
このように、不動産投資で得た物件を相続する際の節税につながります。
なお、以下の記事では相続税について詳しく解説しています。気になる方はご覧ください。
不動産投資で相続税をおさえる方法とは?現物分割で相続の手間を減らそう
リスクを抑えるなら「不動産クラウドファンディング」がおすすめな理由3選
不動産投資は現物の不動産投資以外にもさまざまな方法があります。
そのなかでもリスクを抑えたい方におすすめなのが「不動産クラウドファンディング」です。
その主な理由は以下の3点です。
1.少額から投資できる
2.投資家に有利な投資方法がある
3.国が不動産クラウドファンディングを促進している
それぞれ解説していきます。
1.少額から投資できる
不動産クラウドファンディングは1口1万円からと少額で投資できるものが多く、投資から利益配分の受け取りまでを、インターネットで完結できます。
不動産投資は、株式投資などに比べてハードルの高い投資と言われています。
一方で不動産クラウドファンディングは1口1万円から投資が始められるため、投資初心者でも始めやすいのが特徴です。
2.投資家に有利な投資方法がある
投資家のリスクを抑える「優先劣後方式」が採用されているのも特徴です。
優先劣後方式は、損失が発生した際に事業者の出資金から優先的に損失額を補填するというものです。
そもそも不動産クラウドファンディングでは、複数の投資家と事業者が共同で不動産投資を行うという仕組みです。
そのため、投資家は出資金に応じた利益配分を受け取れます。ただ、不動産クラウドファンディングでも損失が起こる場合があります。
そこで優先劣後方式が採用されていれば、発生した損失を事業者の出資金から優先的に補填するため、事業者の出資金を超える損失が発生しない限り、投資家は損失を被りません。
このように、出資額も1万円からと手軽なうえ、投資家の損失を最小限に抑えていることから、リスクを抑えた不動産投資をしたい方におすすめの投資方法です。
優先劣後方式についての詳しい記事はこちらをご覧ください。
3.国が不動産クラウドファンディングを促進している
最近、日本では不動産クラウドファンディングが注目を集めています。
その背景には、政府のサポートや規制の緩和があります。
たとえば、金融庁はクラウドファンディングのルールを見直して、もっと多くの人が参加しやすくなるように環境を整えてきました。
特に、少額から投資できる仕組みが整ってきたことで、「投資はハードルが高い」と感じていた個人でも始めやすくなっています。
また、セミナーやオンライン講座など、投資に関する学びの場も増えてきており、知識ゼロからでもしっかり理解できるようになってきました。
こうした取り組みによって、安全性や透明性も高まり、不動産クラウドファンディングは信頼できる投資先として認知されるようになっています。
なお、不動産クラウドファンディングについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
不動産クラウドファンディング市場拡大中!その理由とメリット・デメリットを解説
「えんfunding」で不動産投資を始めよう
リスクを抑えた不動産クラウドファンディングを始めたい方は「えんfunding」がおすすめです。
1口1万円からと少額投資が可能なうえ、スマートフォンからいつでも運用状況を閲覧できるため、初心者の方でも安心して始められます。
また、えんfundingでは投資家に運用レポートが提供されるため、不動産投資の知識やノウハウを身につけたい方にも向いています。
リスクを避けた不動産投資を、えんfundingで始めてみてはいかがでしょうか。
不動産投資が学べる漫画など特典プレゼント中
漫画だから分かりやすい。不動産投資が学べる特典を無料プレゼント。お申込みはこちらから。
特典提供元:株式会社えん


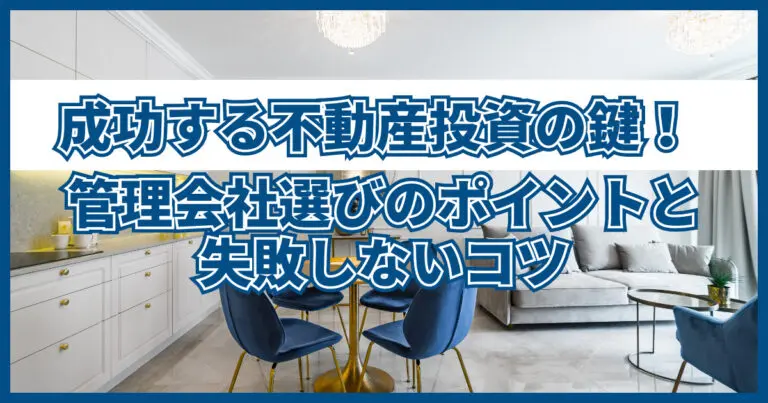
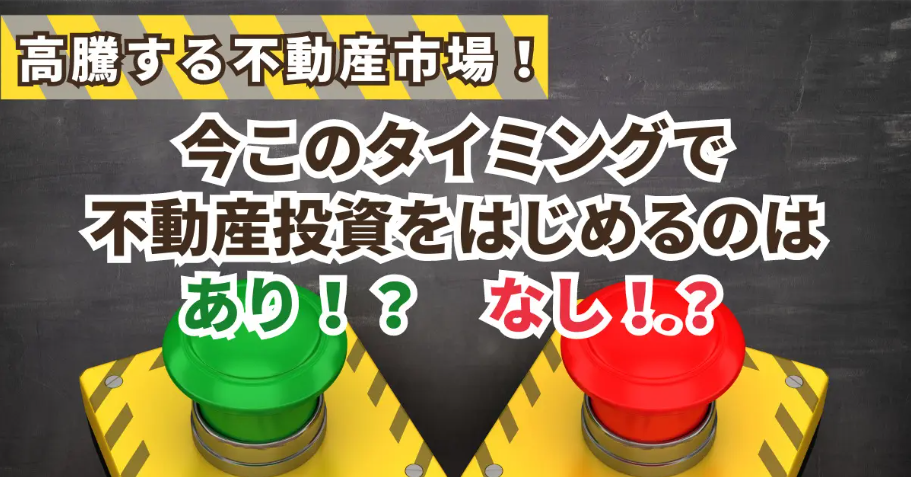


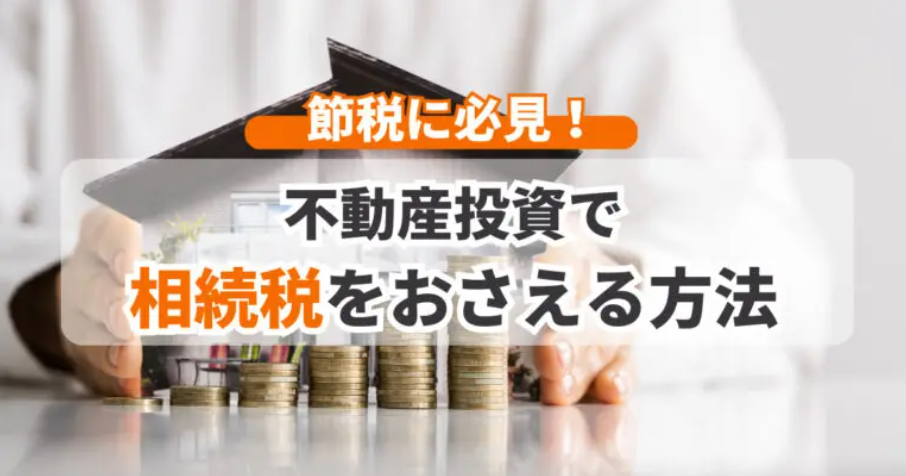

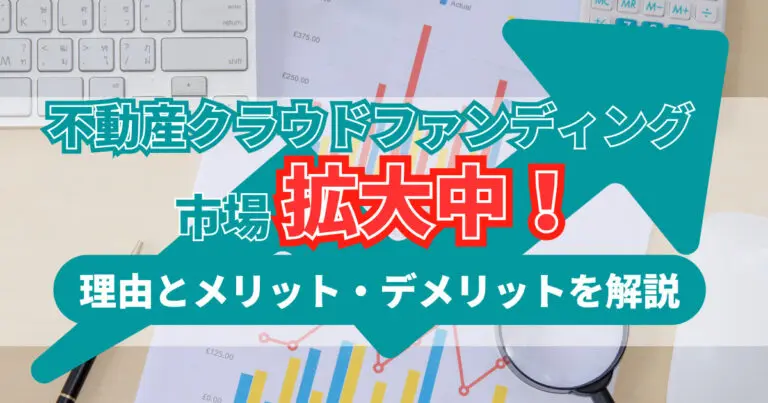
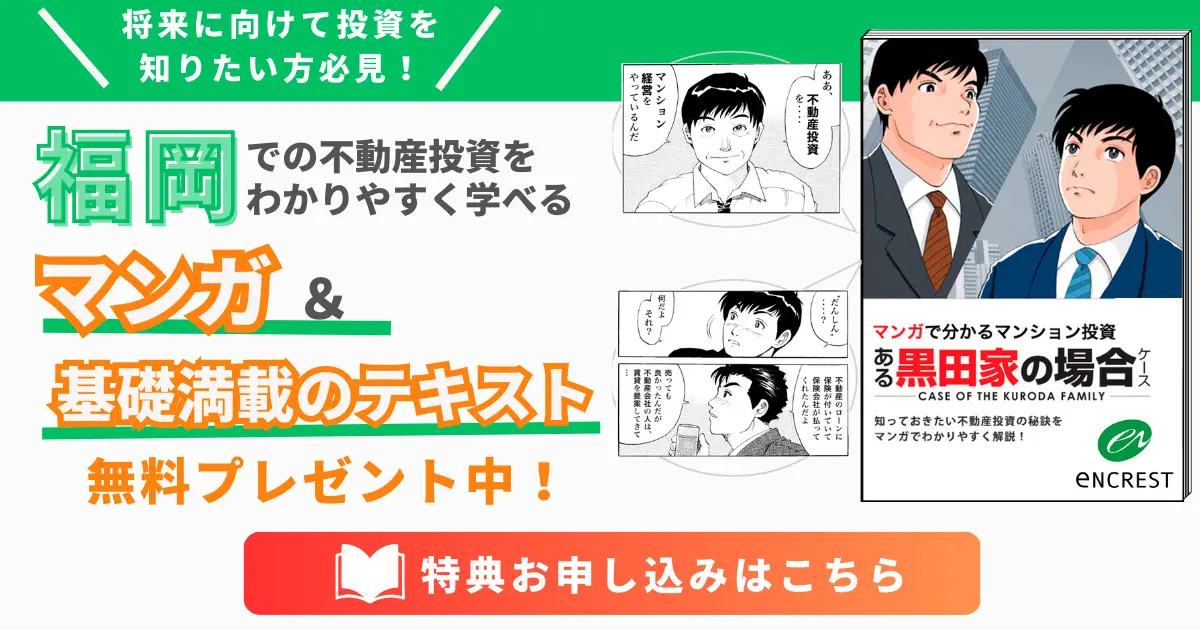

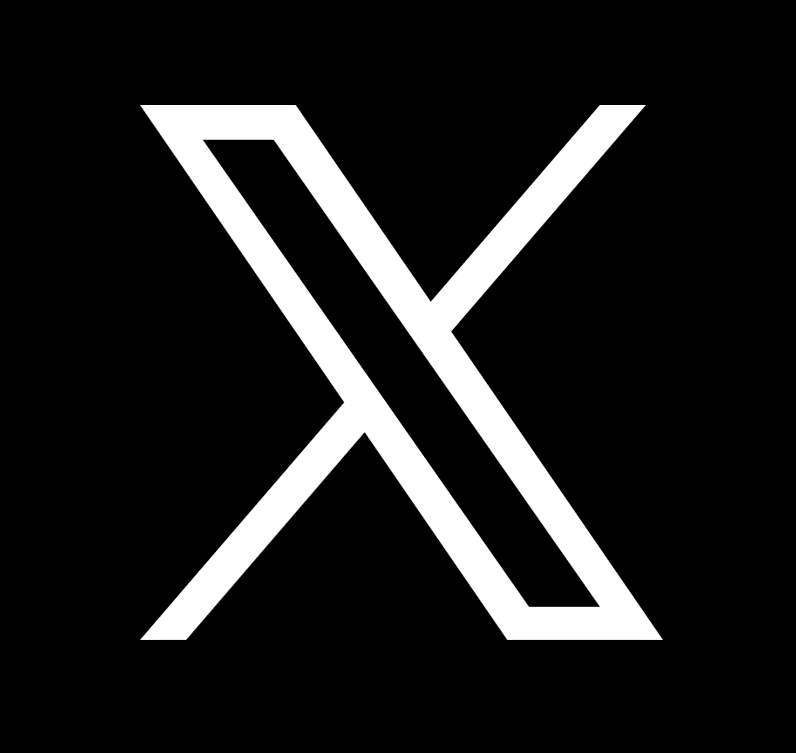
 関連コラム記事
関連コラム記事
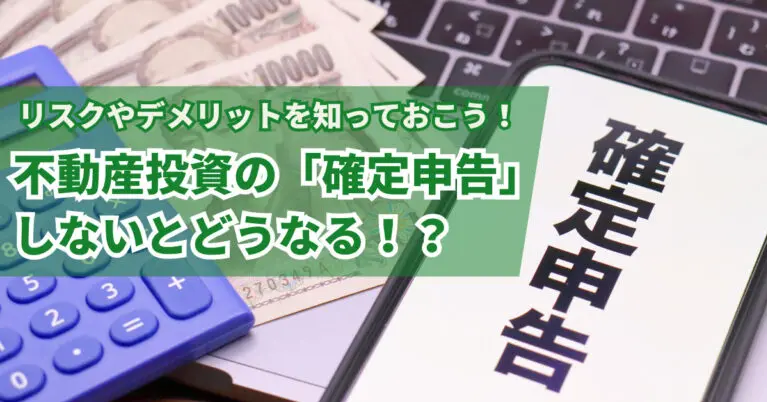
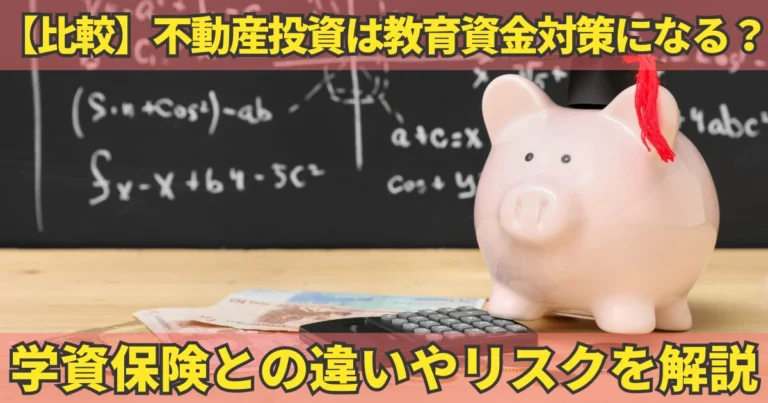
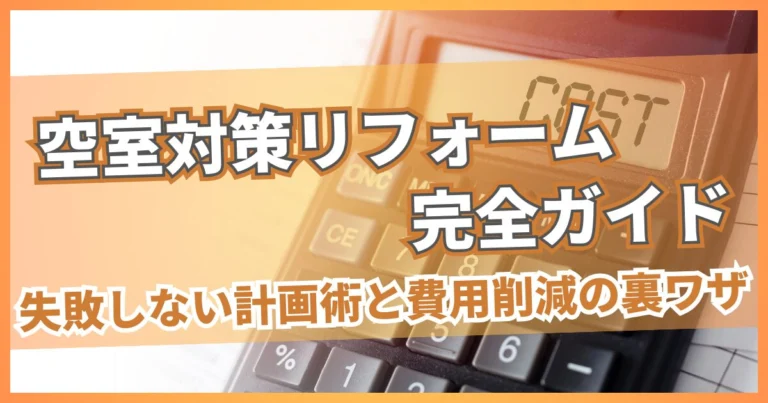
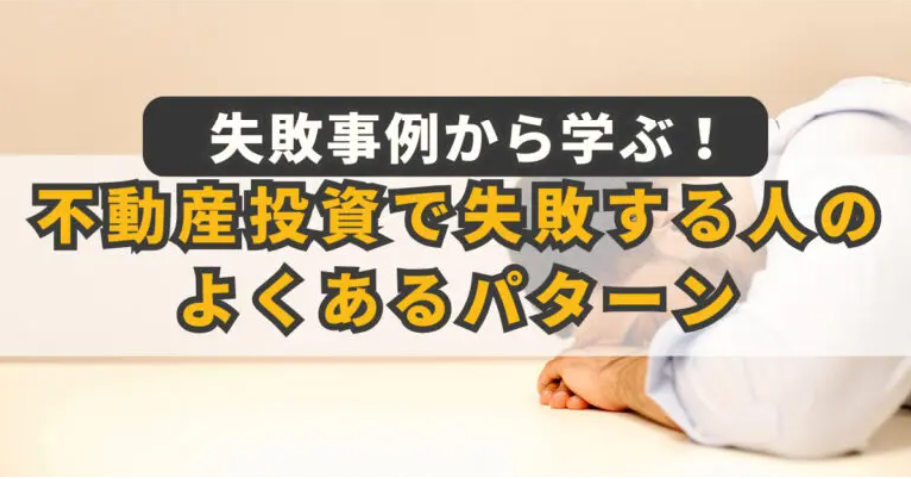


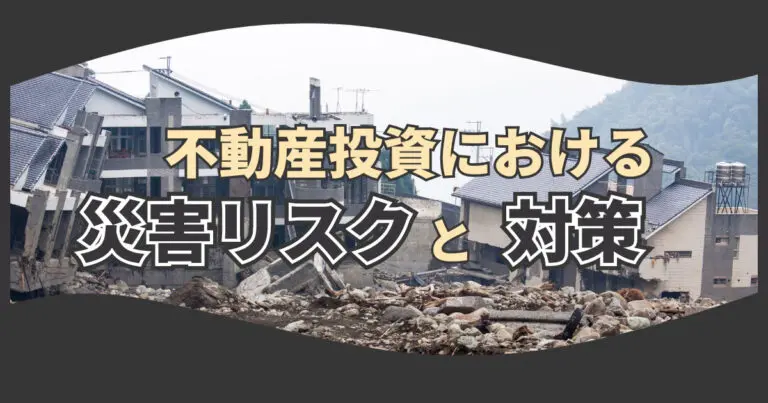

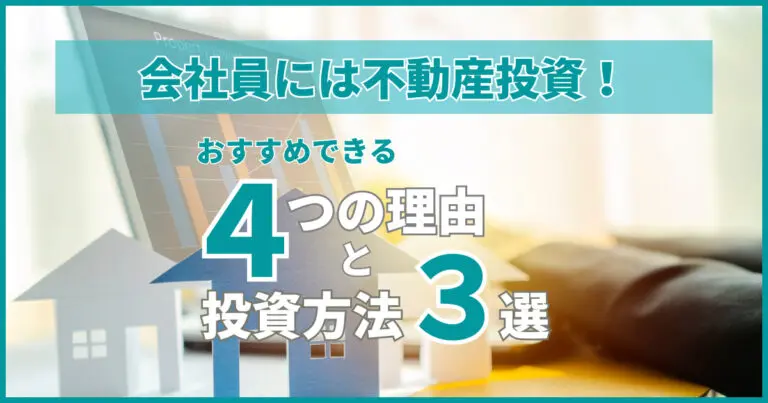
 人気コラム記事ランキング
人気コラム記事ランキング